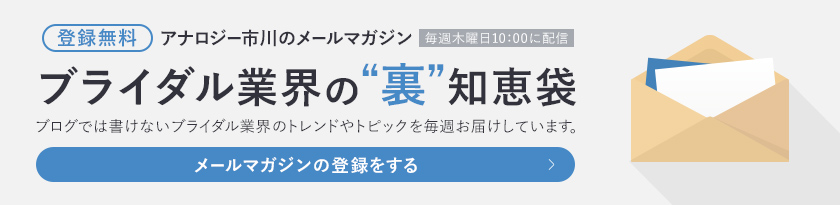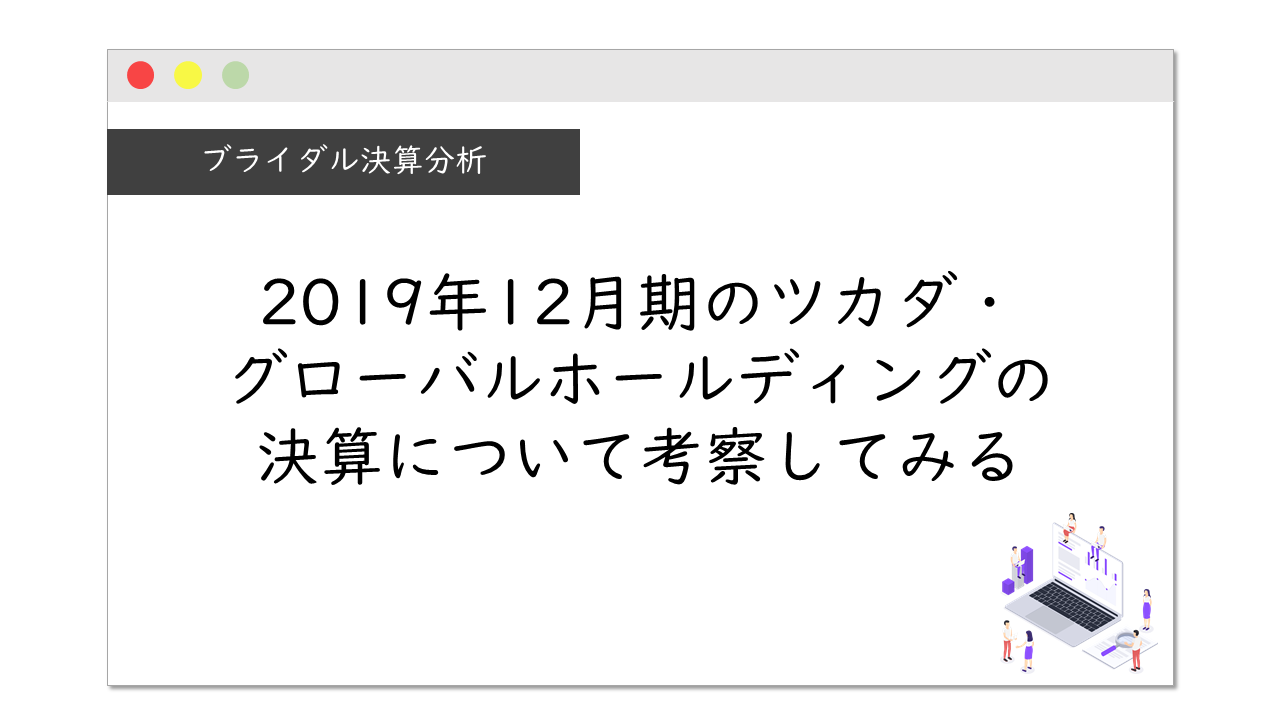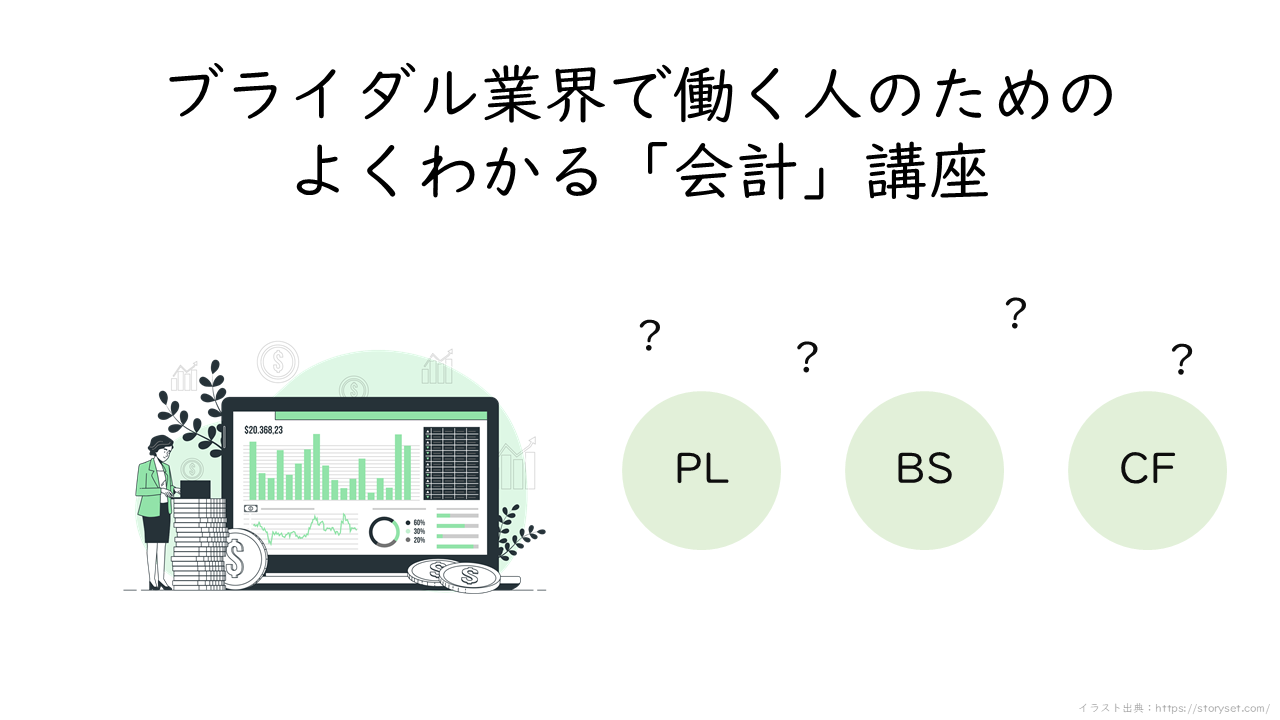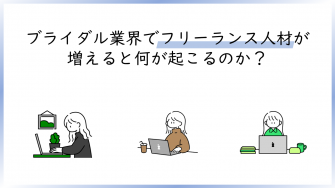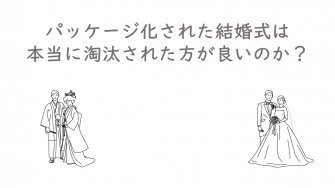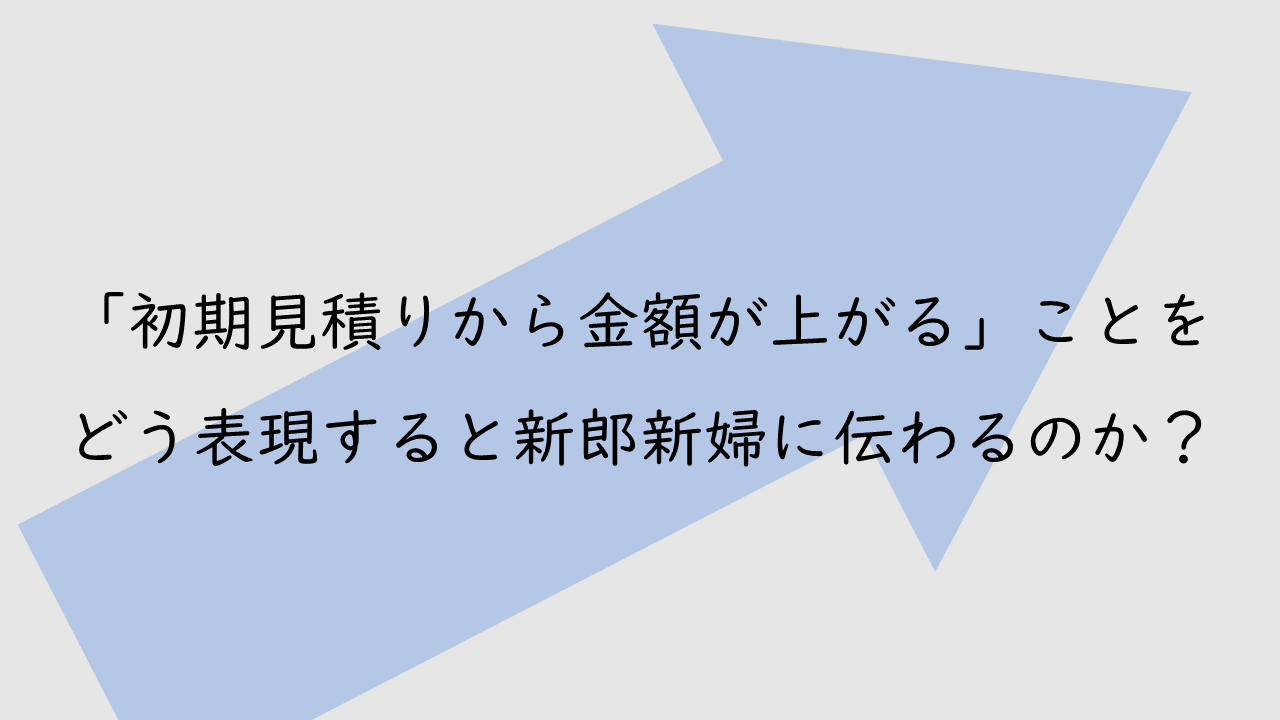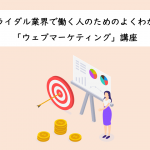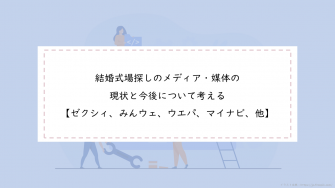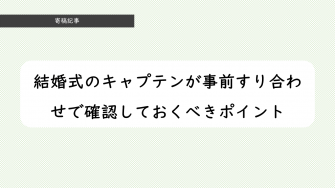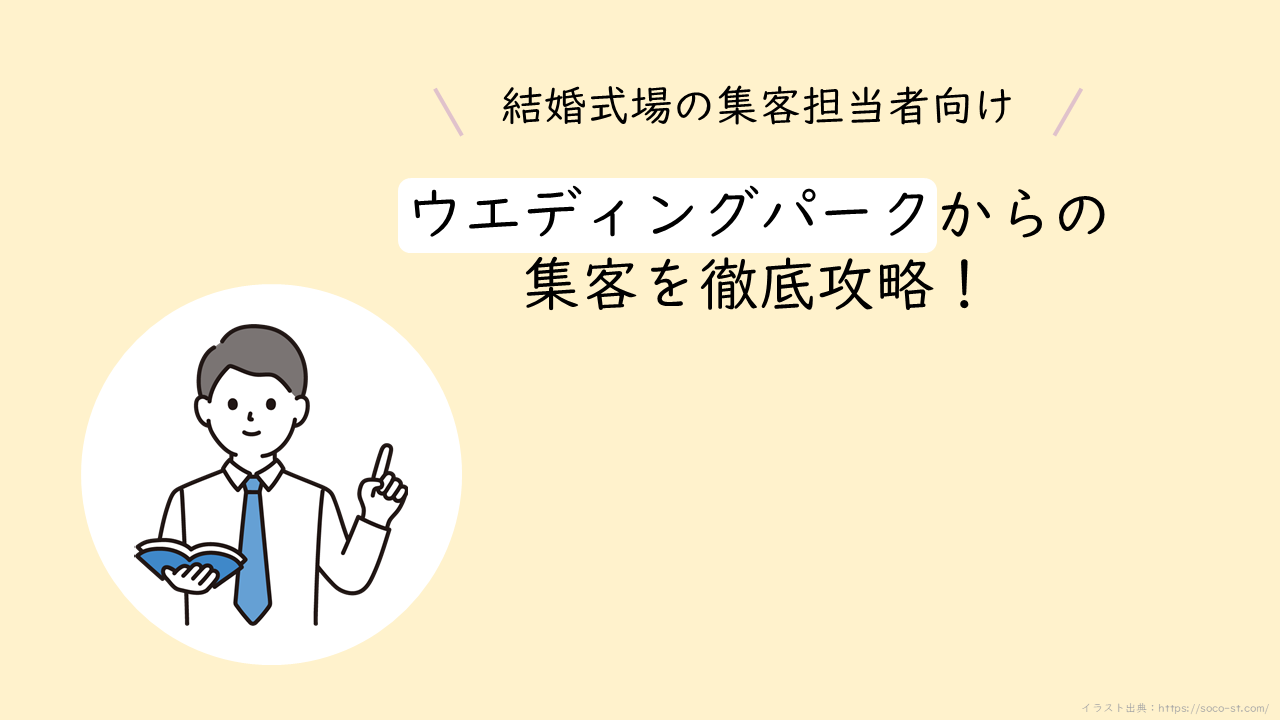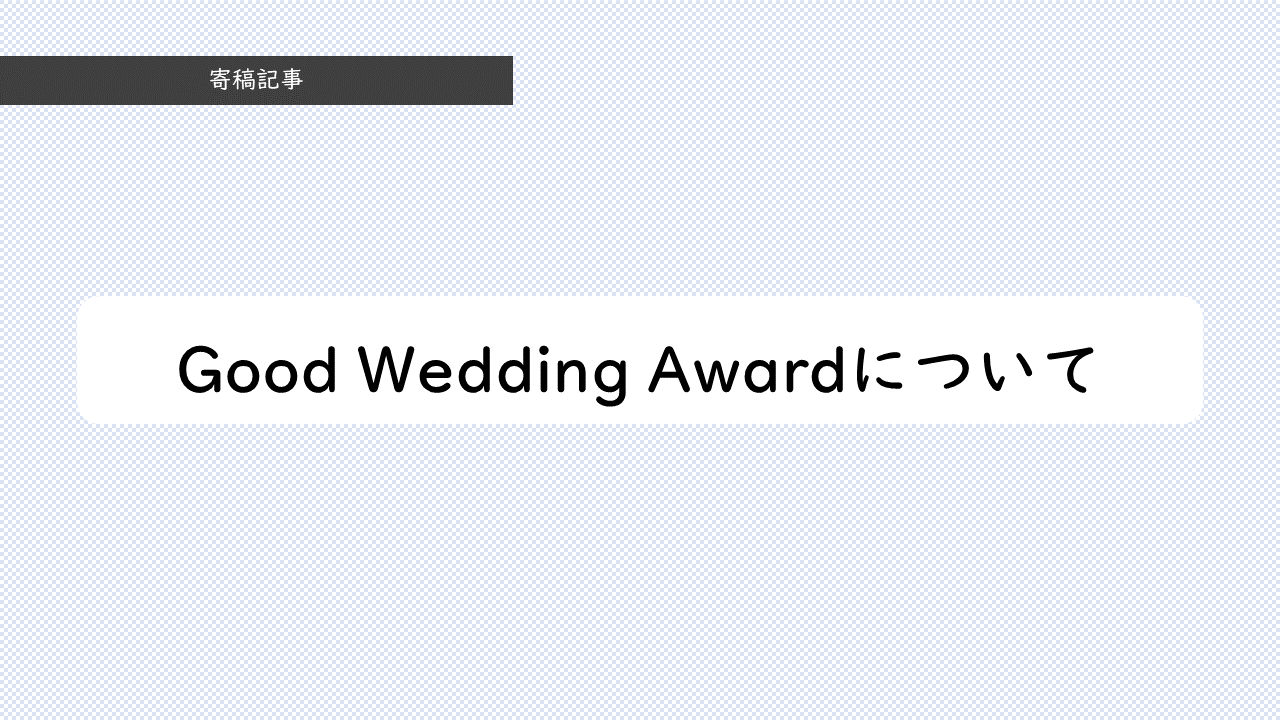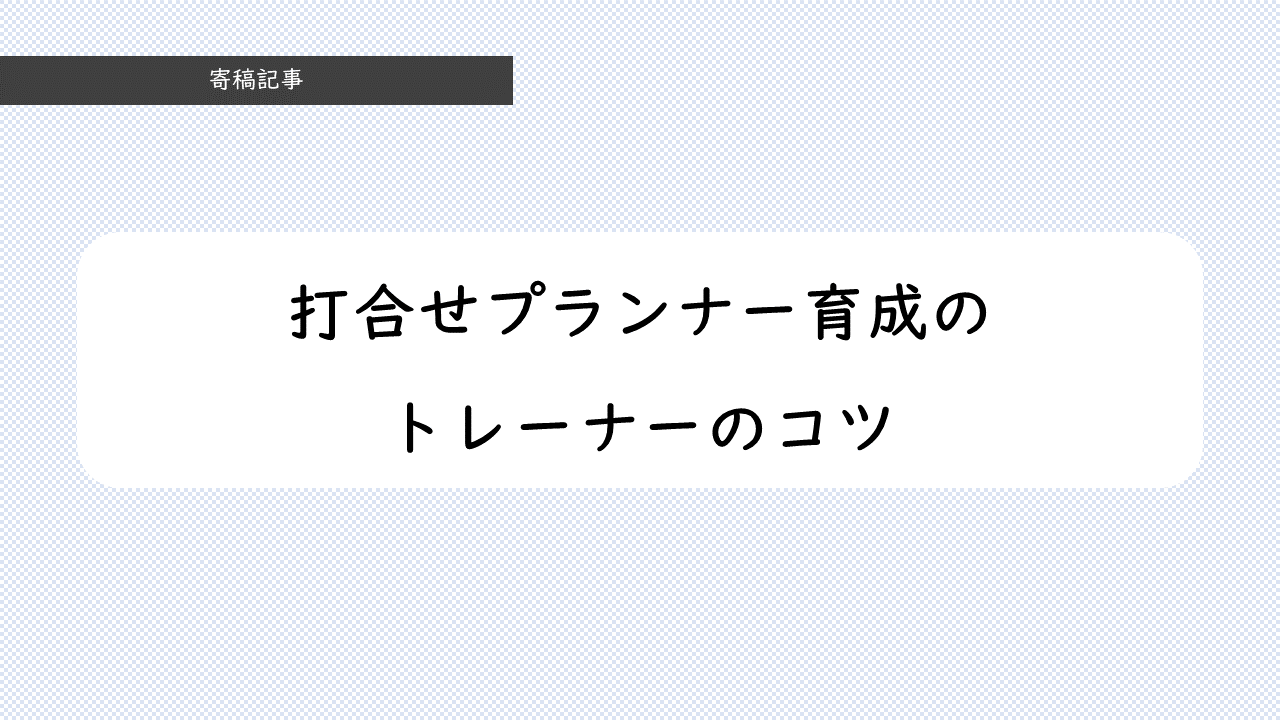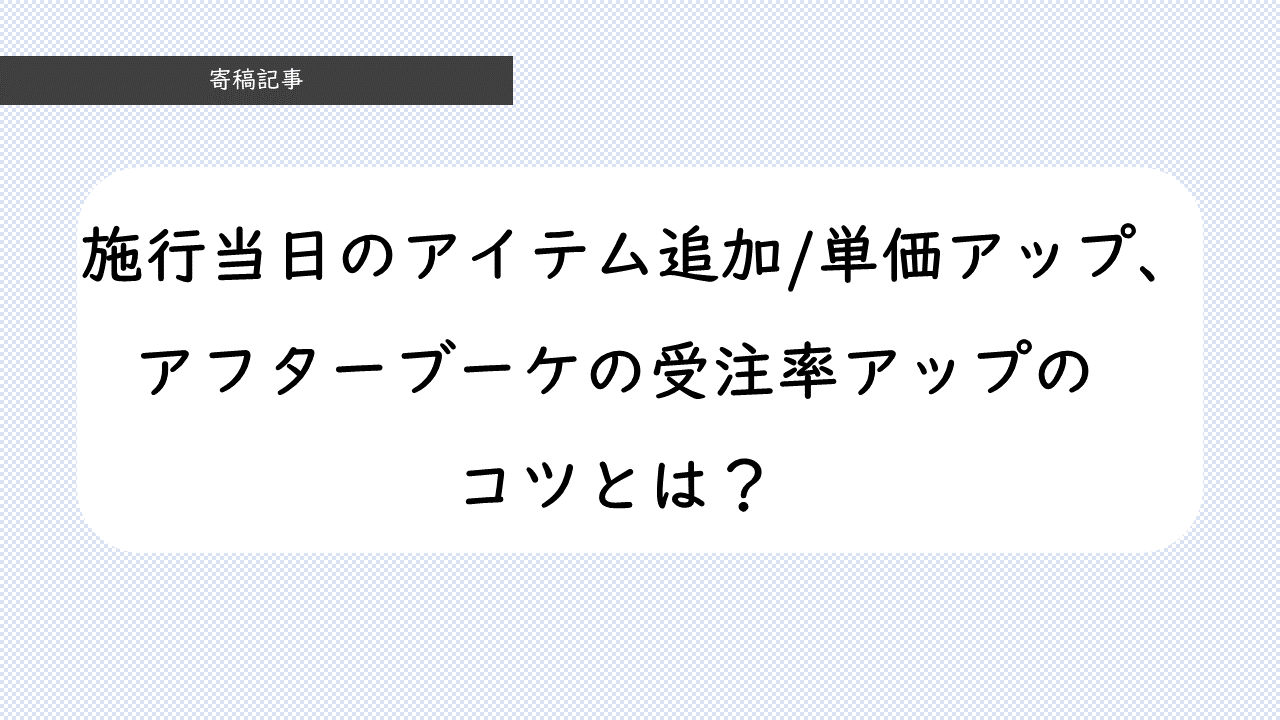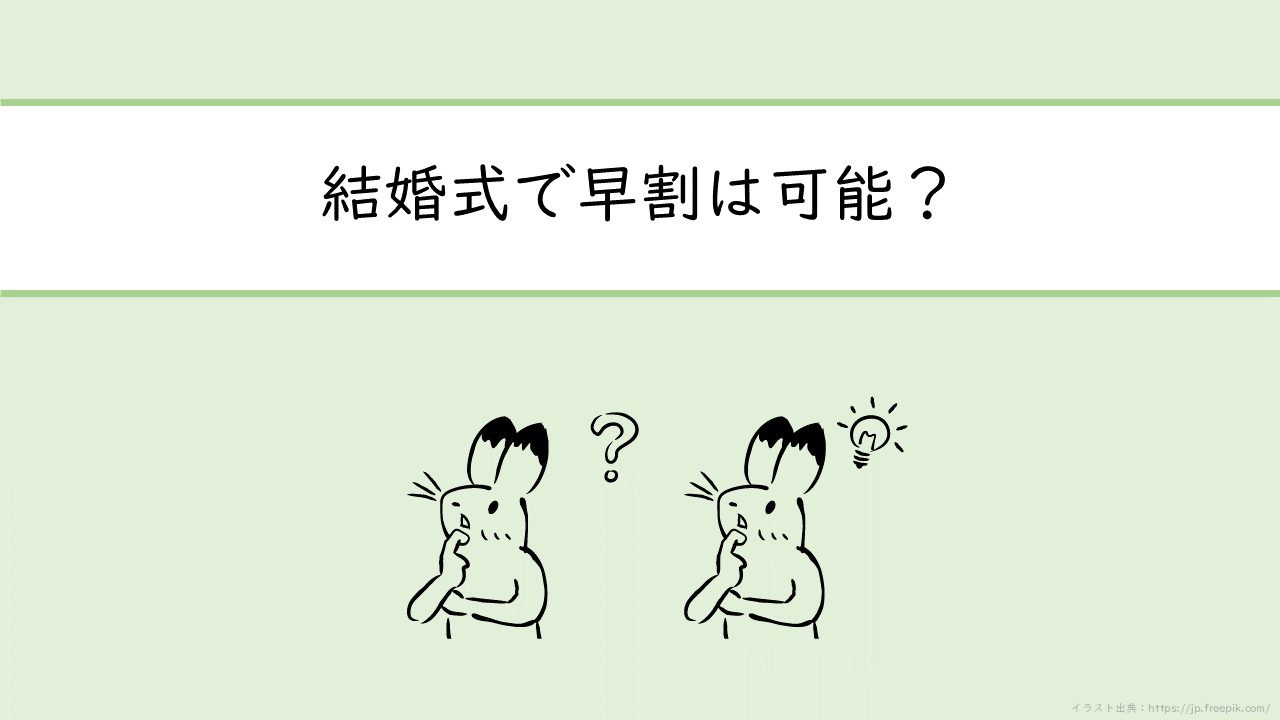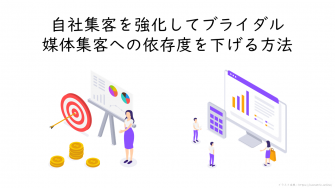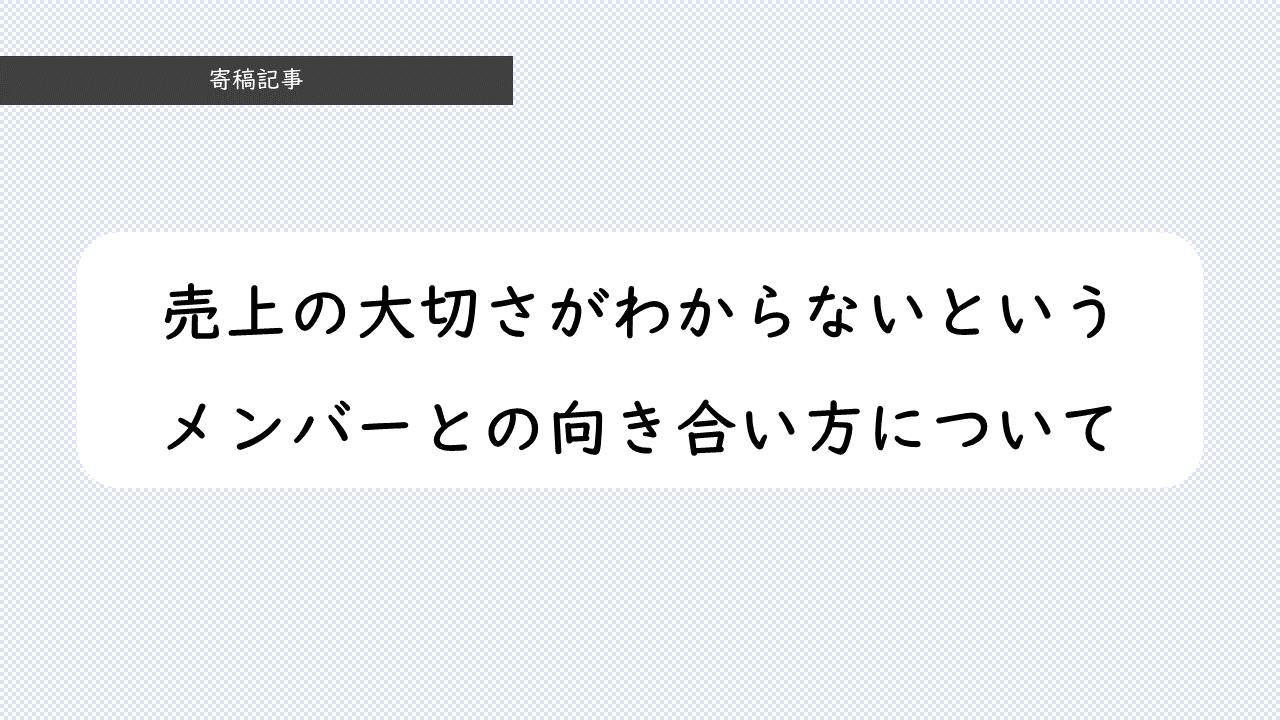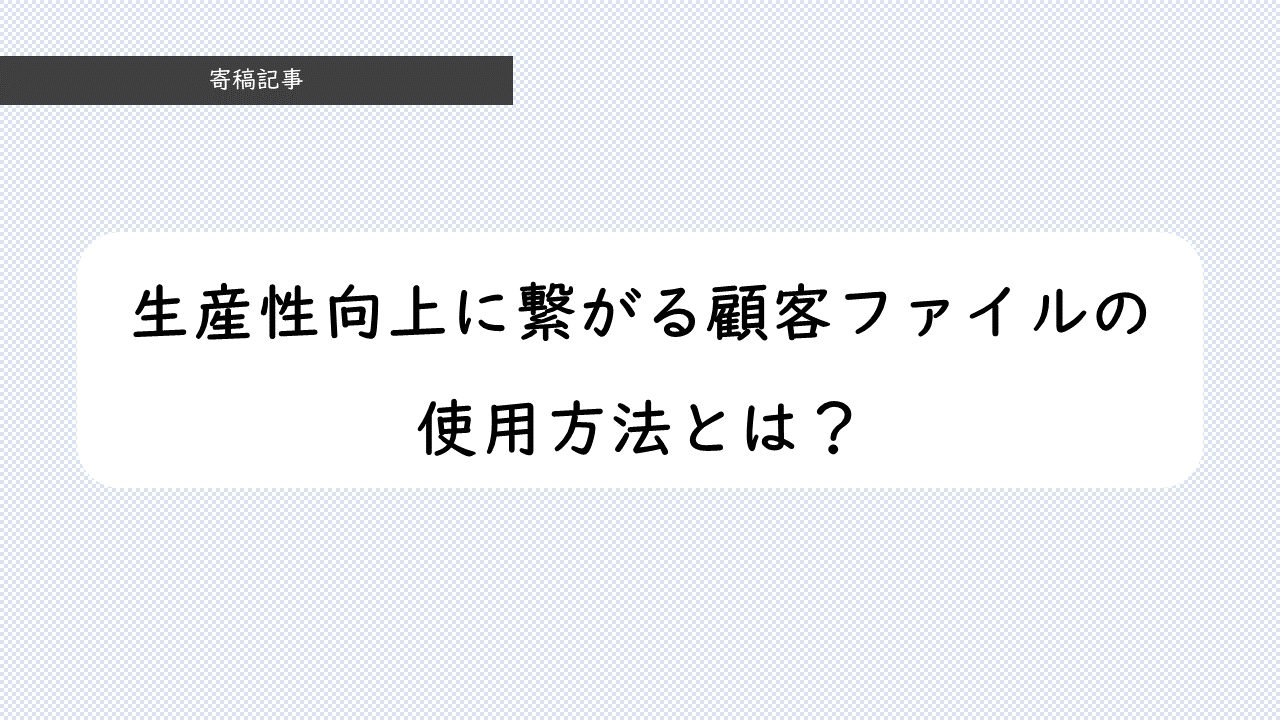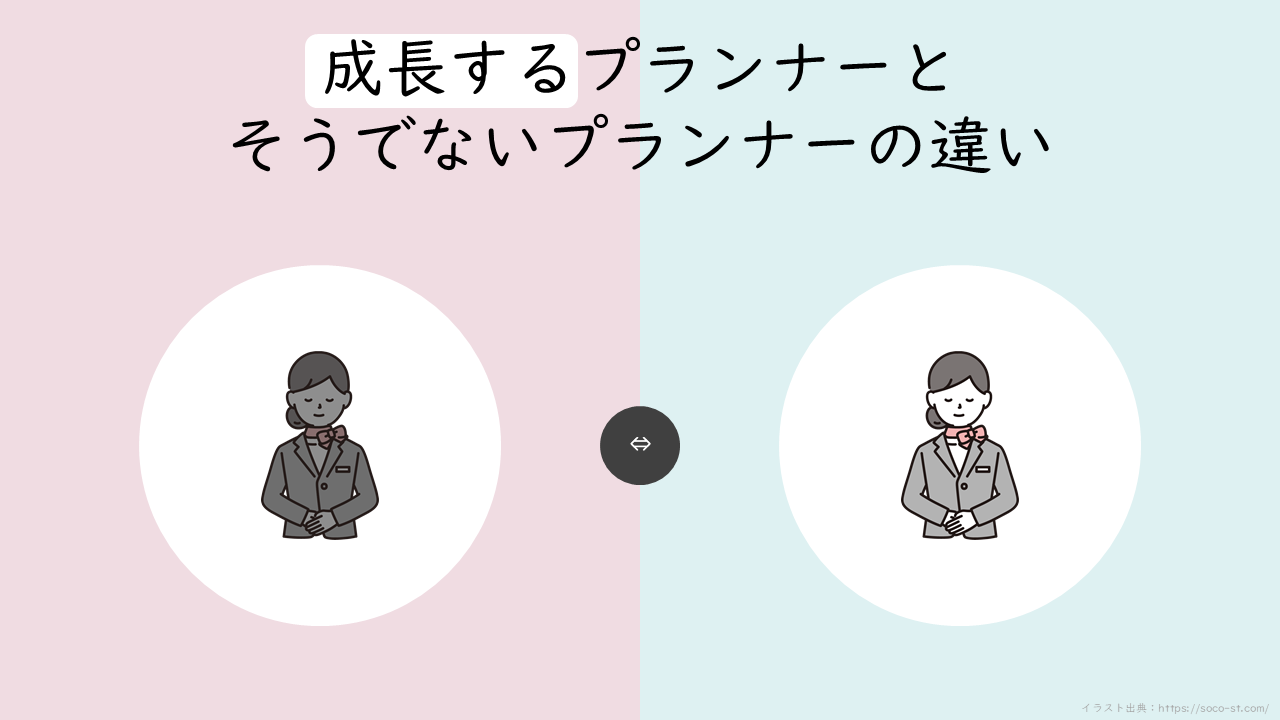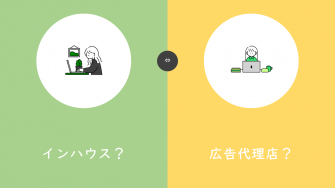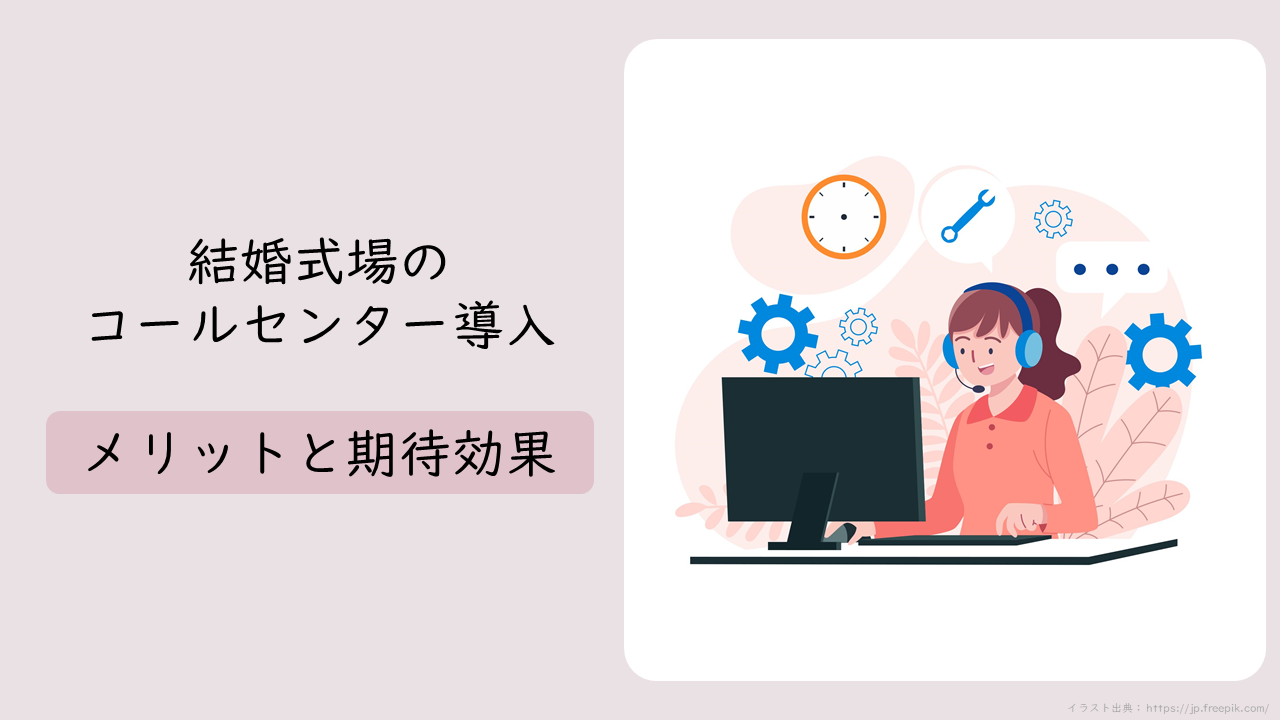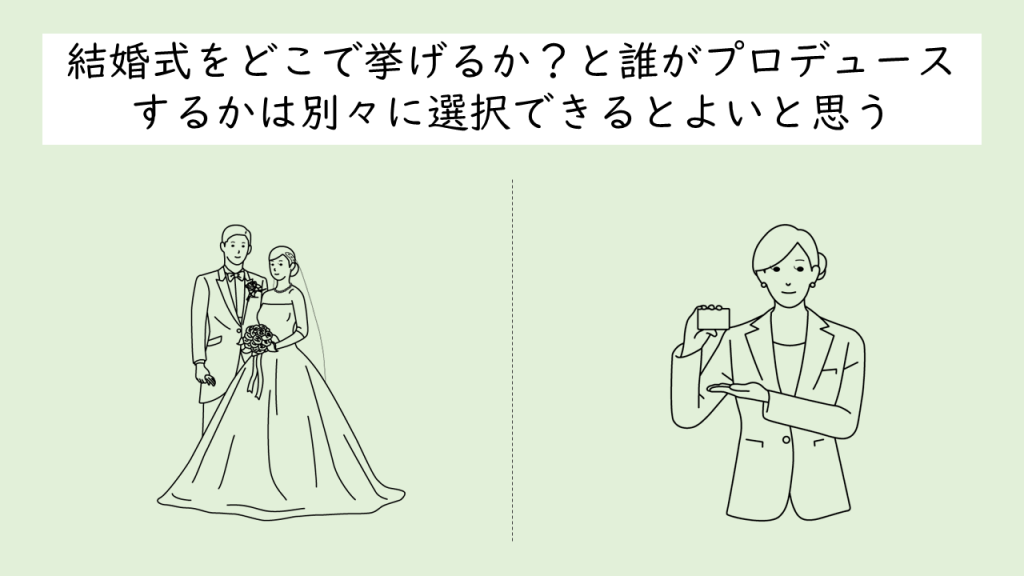
アナロジーの市川(@analogy_ichitk)です。
フリープランナーの増加や顧客ニーズの多様化などの背景から、今後の結婚式づくりの方法について考えてみます。
目次
どこで挙げるかとプロデュースの概念
これまでのブライダル業界では会場とプロデューサーが一体化していること(同じ企業が運営している)ことが前提と考えられていました。
例を挙げると以下の通り。
- 青山迎賓館はT&Gが会場を持っていて、かつT&Gのプランナーが結婚式をプロデュースする
- ラグナヴェールTOKYOはエスクリが会場を持っていて、かつエスクリのプランナーが結婚式をプロデュースする
- IWAI OMOTESANDOはCRAZYが会場を持っていて、かつCRAZYのプロデューサーが結婚式をプロデュースする
※「会場を持っている」の表現については厳密に物件・土地オーナーというわけではないことがほとんどですが、現状ではこれ以上に適切と思われる表現が思いつきませんでした。
これは、結婚式をするためにはまず最初に会場から選ぶことが一般的だったので、「どこで誰と結婚式を創るか?」をセットで選ぶスタイルと言えます。
一方、近年はプロデュースサービスやフリープランナーなど、会場を持たずにプロデュースのみを専門で行うチームや人が増えてきました。
- 格安系であればスマ婚や楽婚など
- 少人数系であれば小さな結婚式や家族挙式など
- オリジナル系であればHAKU、花ノ結婚式屋、フリープランナーの方など
この方法で結婚式を挙げる場合は、まずプロデュースに問合せて契約、その後または同時に会場を提案してもらって会場も決定、という流れになるので、「誰と創るか」と「どこで挙げるか」を別々に選ぶスタイルと言えます。
独立型プロデューサーの増加、会場運営企業側の業績的観点、顧客側(カップル側)のニーズ変化。これらの背景から、「結婚式において会場選択とプロデューサー選択は別々で行うもの」という考え方は広まっていくのではないかと予想していますし、個人的にもそうなったほうがいいと考えています。
同じ会場でもプロデューサー次第で結婚式は違うものになる
- @目黒雅叙園 produced by 目黒雅叙園プランナー
- @目黒雅叙園 produced by 小さな結婚式
- @目黒雅叙園 produced by スマ婚
- @目黒雅叙園 produced by フリープランナーAさん
※目黒雅叙園がフリープランナーの利用を許可しているかどうかは知りませんが例として挙げさせていただきます。
上記1~4はいずれも同じ会場ですが、おそらく内容としては全く異なる結婚式になると思います。価格、料理、ドレス、アイテム、進行、空間装飾、当日までの段取りなど、様々な点で違いがあるはずです。
しかし当日列席したゲストは、プロデューサーが誰だったのかを知る由はありません。「目黒雅叙園の結婚式に列席した」と認識されるはずです。
なおゲストに限らず実際に結婚式を挙げたカップルも、自分たちの選択以外のプロデューサーで結婚式をやっていたらどうなったのか?を知ることはありません。
結婚式は基本的に人生に1回だけですし、複数回挙げることになったとして前回と同じ会場で挙げたいと思う人はほぼいないでしょう。
もっというと、各選択肢でプロデュースを担当している会社や個人が、他のプロデューサーがどのようにしているかの詳細を知らないことも多いと思います。
つまり、同じ会場の結婚式でもプロデューサー次第で内容は変わると言えるものの、意図して伝えない限りはゲストがプロデューサーを知る機会もなく「この会場の結婚式に列席した」と記憶されはずであり、また結婚式を挙げたカップルも、「もしも他のプロデューサーに依頼していたらどうなったのか?」知ることはないと言えます。
ついでに言うと、プロデューサー自身も他社のプロデュースの詳細は知らないので説明できないことがほとんどでしょう。
個別選択実現へのハードル
冒頭でも書いたように、個人的な意見としては
・今のように「●●会場(produced by ★★)」のようなパッケージで選択
よりも
・「●●会場」で「★★プロデュース」(ただし選択の前後は問わない)
のように別々で選択肢があって、その組み合わせを選べる方がカップルにとってはよいと考えています。
※現状のように会場とプロデュースが同じ企業の場合はそれを明示したらよい(青山迎賓館 produced by T&G etc)のかなぁと。
理由は、結婚式において会場に紐づく要素とプロデューサーに紐づく要素が異なるので、別々の方が個人の希望内容ごとに最適な選択が取れるようになるからです。
しかし、今の業界環境下でこの個別選択を実現しようとすると様々なハードルがあります。
- 主要メディアにプロデューサーに関する情報掲載がない
- どの会場だとどのプロデューサーに依頼できるのかの網羅的な情報が整理されていない
- 契約条件やプロデューサーを変えることによって何が違うのか?が複雑すぎる
- なので顧客(カップル)が理解するのがかなり難しい
- 会場側からすると見ず知らずのプロデュースやフリーランスを信用できない
- プロデューサー側からすると顧客が希望していても会場側から断られることもザラにあるし、事例として公開できない
などなど。
そして最も懸念というか難しそうだと思うのは、そもそも会場側はそんな選ばれ方を求めていないところがほとんどなのでは?ということ。
複数社(複数者)が1つの会場に出入りするようになると、ブランディング、セキュリティ、リーガルなどの面で管理しなければいけないことが著しく増えます。
会場利用の集客チャネルが増えることはメリットではあるものの、それ以上にデメリットの方が大きいと判断する会場が大きいだろうなぁという気がしています。
特にウェディングを専業またはメイン事業として運営している大手企業はどちらかと言えば内製化が今のトレンドですから、それとは逆行する流れになりますし。
難しいかなぁ。
個別選択実現に向けた取り組みは?
- 会場を選ぶメディアはもうある
- フリープランナーやクリエイターを探すサイトももうある
- 公開されているかはさておき、様々な会場×プロデューサーの事例もある
このように、情報や実例の要素自体はすでにあるんですよね。
なので完全にゼロから作るというよりは、今ある情報の組み合わせ方と発信の仕方を変えることが必要というイメージ。あとは情報自体をちゃんと整理することも必要ですね。
企画してトライアルでやってみる、少しずつ業界と顧客の理解を得る、利用比率が増える、文化が変わっていく。
もし実現するとしたらこんな流れでしょうか。
実はいろいろ考えていて少しずつ自社でも動かし始めてはいるんですが、やってみて思ったのは少なくとも数年かかりそう。
今アナロジーで運営しているWedding Me関連サービスはいずれ相互に連携してこの世界観を実現することを目指しています。まだまだ具体的な形になっているとはいいがたいですが、今後も企画実行検証を繰り返して少しずつ形にしていこうと思います。
会場選びとプロデューサー選びの選択方法について今回のまとめ
フリーランスの人も増えるし、顧客ニーズも多様化するし、業界自体も縮小する。
この将来予測を考えると、ハードと人材は流動化させた方が柔軟性や機動性は高まると思うんですよね。
もちろんこれは全体論であって個別事象についてもちゃんと考慮した丁寧な仕組みづくりが必須ではあるものの、今の延長線上に明るい未来があるとは言い難いと思うので、新しい考え方はこれからも積極的に取り組んでいきます。